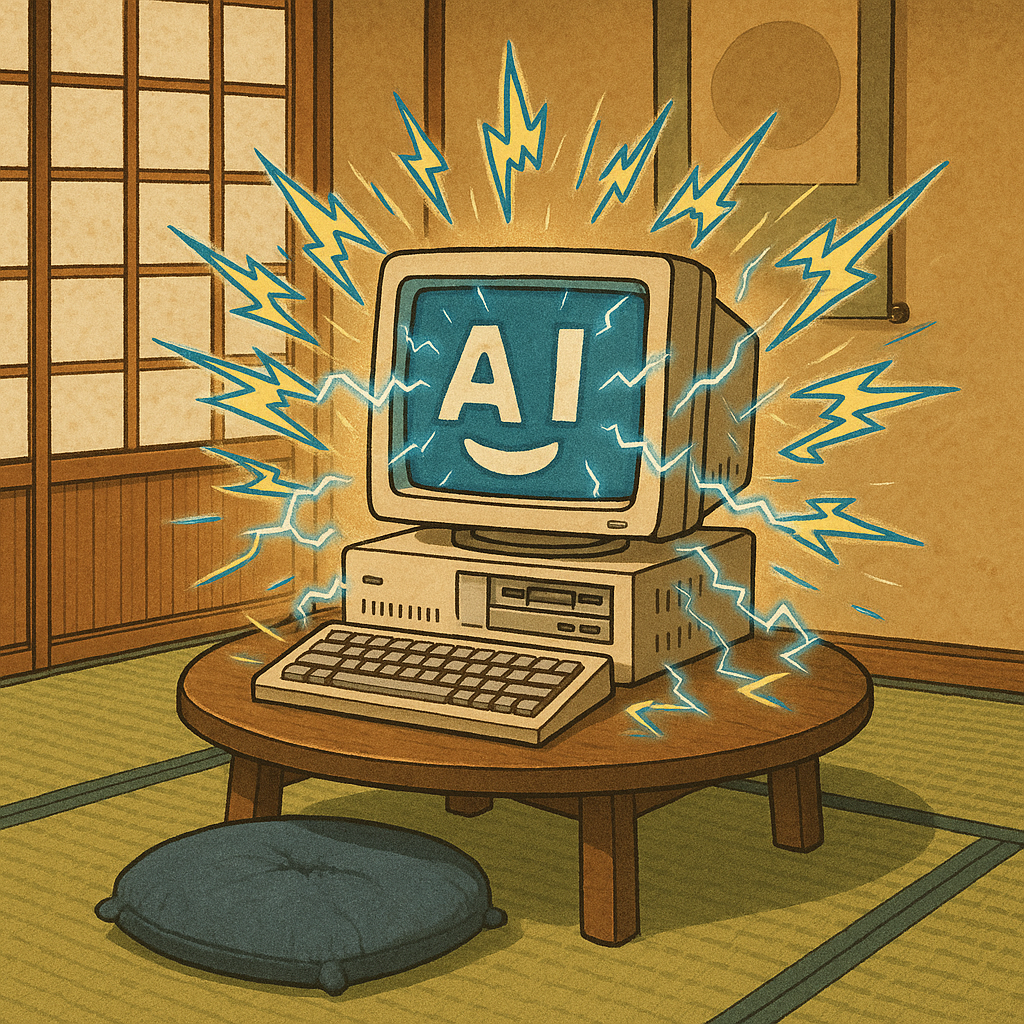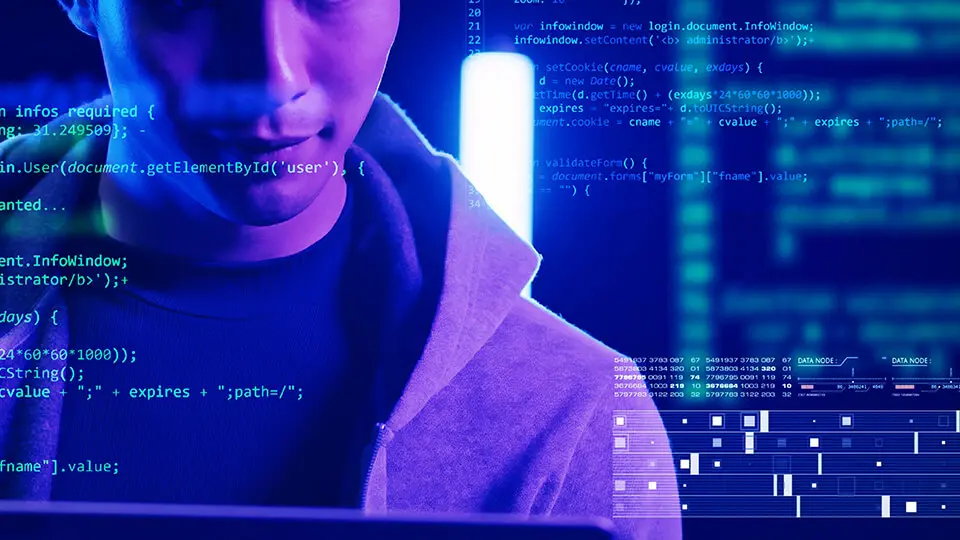アプリ開発日誌
2025.04.25
システム開発者が驚いた!AI作曲アプリ「SUNO」が楽しすぎる件

普段はアプリや業務システムを開発するシステムエンジニアとして働いており、AIの活用も日常的に行っています。ChatGPTやGitHub Copilotなど、開発現場におけるAIの存在はもはや欠かせないものとなっています。
そんな私が最近出会って衝撃を受けたのが、AI作曲アプリ「SUNO」です。
このアプリ、まさに「未来そのもの」。単なるおもしろツールにとどまらず、AIの進化と可能性を強烈に感じさせる体験ができました。
SUNOとは?AIが作曲からボーカルまでこなす時代
「SUNO」は、テキストを入力するだけでAIがオリジナルの楽曲を自動生成してくれるアプリです。
たとえば、「夏の終わりの切なさを表現したJ-POPバラード」などといったプロンプトを英語で入力するだけで、数十秒〜1分程度で1曲が完成。しかも、歌詞、メロディ、編曲、ボーカルまですべてAIが生成してくれるという驚異的な仕様です。
使い方は非常にシンプル。
無料プランでも1日数曲の生成が可能で、クオリティを確かめるには十分な体験ができます。
公式サイトはこちら(https://suno.com/home)
実際に使ってみた体験談
私もさっそく、SUNOで曲を作ってみました。
最初のプロンプトは、「ノリが良くて格好良い曲」。
この1文を入力しただけで、わずか30秒ほどでハイクオリティな楽曲が完成。イントロからノリの良いシンセベースが響き、ボーカルが流れ出した瞬間、思わず「え、ここまで来てるの?」と驚愕しました。
特に印象的だったのは、メロディと歌詞のマッチングの自然さと、AIボーカルの滑らかさ。
従来のボーカロイドや音声合成よりもはるかに人間らしく、自然な抑揚やブレスも表現されており、「これは商用でも使えそうだな」と感じるレベルでした。
英語の歌詞で作られた楽曲は自分で生成していなければ、生成された楽曲だとは気付けない自信があります(笑)
技術者として感じた驚きと興味
システム開発者としての視点で見ると、SUNOが実現している技術には本当に興味深い点が多いです。
おそらく、生成AI(特に拡散モデルやトランスフォーマー系のアーキテクチャ)をベースに、音声合成(TTS)、自然言語処理(NLP)、音楽理論に基づく構造生成などが統合されていると推測されます。
しかも、それを数十秒でユーザーに提供できるUX設計には、相当な最適化とエンジニアリングの工夫があるはずです。
また、ボーカル部分については、最新のVoice Cloning技術やNeural Vocoderが活用されている可能性もあり、AIがただ歌うだけでなく「感情を込めて歌っているように聞こえる」仕上がりになっています。
音楽の民主化を感じた瞬間
SUNOを使って感じたのは、音楽制作の民主化が本当に現実になったということ。
これまでは作曲には専門知識が必要で、歌を入れるには録音環境や人材も必要でした。
しかしSUNOがあれば、誰でも数分で“自分だけの曲”を作れる時代が来たのです。
しかも、それが趣味で終わらないレベルのクオリティ。
SNSでのシェアも簡単で、「自分の歌」を持つ人が爆発的に増える可能性を感じます。
これはまさに、音楽クリエイションのあり方そのものを変えるインパクトがあります。
AIには、今までスキル不足で立ち入れなかったジャンルに対して、各個人のセンスを武器に“人に見せられるライン”まで押し上げてくれる可能性を感じています。
これまで「才能がないから無理だ」と諦めていたことにも、AIがそっと手を差し伸べてくれる。
そんな優しい未来が、すでに始まっているのかもしれません。
開発者が感じた可能性と課題
可能性は大きい反面、まだ課題も感じます。
たとえば、商用利用時のライセンス問題や、生成した曲の著作権の扱いなど、クリエイターエコノミーとの整合性はまだ発展途上です。
また、現在はプロンプトに英語が必要という点も、日本の一般ユーザーには若干ハードルになるかもしれません。
しかし、こうした課題を超えるだけの「体験の力」がSUNOにはあります。
開発者視点で見ても、「人がインスピレーションを得る道具としてのAI」がここまで来たか、という感動があります。
まとめ:AIは“使える”から“楽しめる”時代へ
SUNOは、単なる作曲ツールではなく、AIと人が一緒に創作する未来の入口のように感じました。
開発現場で使われる業務特化型AIももちろん重要ですが、SUNOのような“エンタメ系AI”こそが、一般層にAIの本当の魅力を届ける存在なのかもしれません。
「AIがこんな曲を作るなんて!」と驚き、
「自分も何か作ってみたい!」とワクワクする。
そんな体験を通して、私自身も改めてAIの可能性を感じました。
音楽に興味がある方はもちろん、開発者の方にも、ぜひ一度SUNOを試してみてほしいと思います。
? SUNO公式サイトはこちら
AIの“今”と“未来”が、きっと見えてくるはずです。